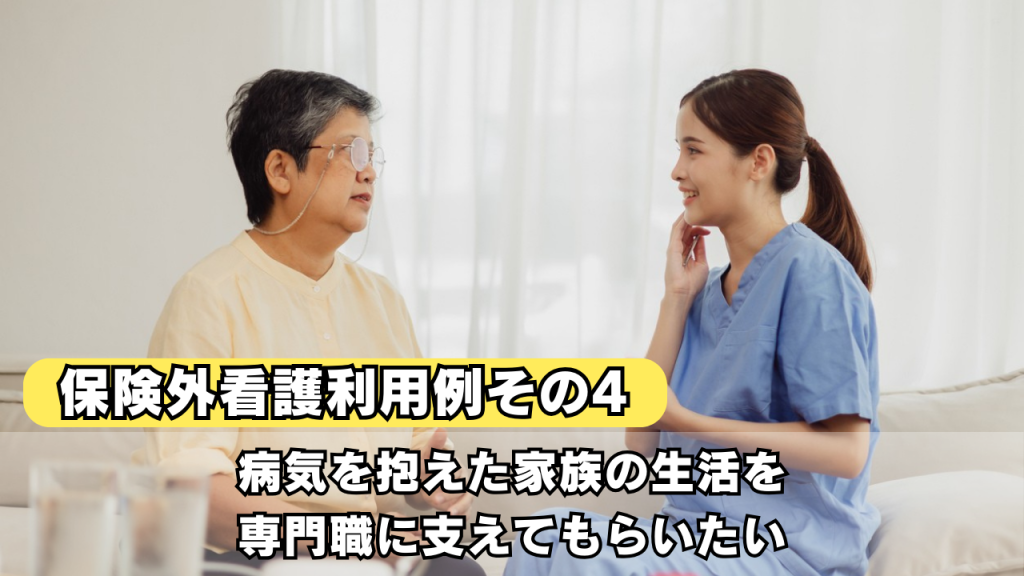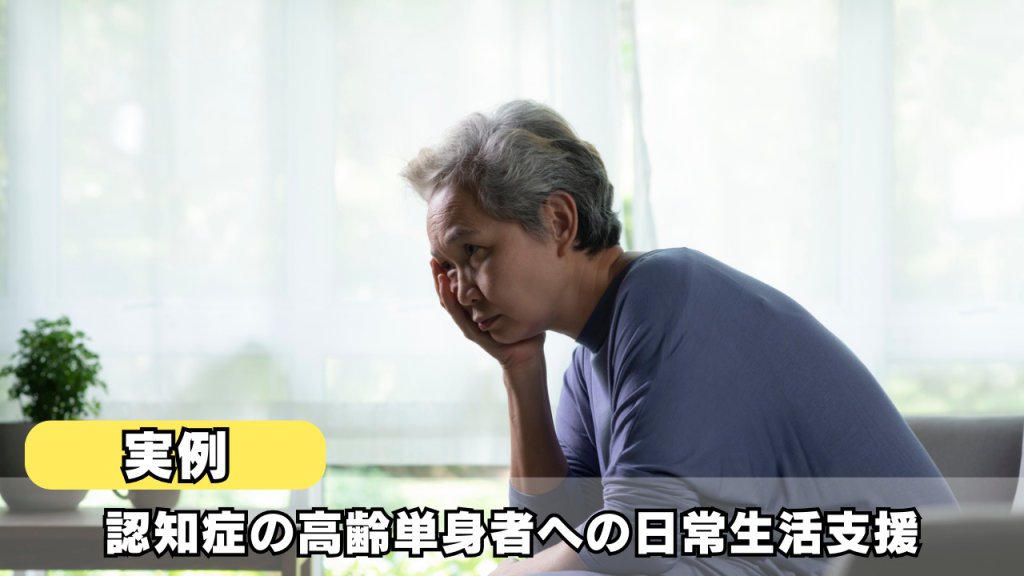全4回にわたり、保険外訪問看護の利用例をご紹介しています。最終回となる第4回目は「病気を抱えた家族の生活を専門職に支えてもらいたい」という場合の保険外訪問看護の活用例です。保険外看護にかかわる看護師として、「こんな支援もあるんだ」と思っていただけるよう、必要としている方にお届けできればと思います。

この記事の目次
1.「生活支援」ってどんなこと?
生活支援とは文字通り生活そのものを支えるという意味です。ただ「生活」と一言で言っても範囲が広く少しイメージしにくいかもしれません。①一般的な視点と②専門的な視点の2点に分けてお伝えします。
①一般的視点
食事、清潔、住環境、睡眠など、基本的な生活が整うことで安定した暮らしにつながります。
a.食事:
栄養バランスのとれた食事や、病気に応じた食事(塩分やタンパク質制限など)、飲み込む力に合わせた調理などが必要です。ただあまり制限ばかりでは彩りや楽しみが減ってしまうため、ご本人の好みや食べる楽しみも大切にします。
b.清潔:
入浴やお体を拭くなど体調に合わせたケアが必要です。清潔な衣服や下着、オムツの交換なども清潔が保てているかを確認します。
c:住環境:
転倒を防ぐため床にものを置いていないか・手すりなどの必要性の有無など、歩行状況を考慮した確認を行います。必要に応じて掃除を行い、清潔で安全な住環境を整えます。
d.睡眠:
「朝起きて夜眠る」という生活リズムが整っているか確認し、状況に合わせたケアを行います。
②専門的な視点
病気特有の症状観察、受診調整、薬の内服状況、そしてこれらの情報をケアマネージャーや訪問看護へ適切に報告・連携します。
a.病気特有の症状:
多岐にわたりますが、体温・血圧・呼吸状態・浮腫・皮膚の状態・排泄状況など様々な状態を看護師の視点で確認します。
b.受診調整:
日々の様子を踏まえて、本人や家族に変わって主治医へ状態を伝えます。また症状悪化時には専門職へ連携をとり、受診日の調整なども行います。詳しくは”保険外看護利用例その1.仕事で病院受診に付き添えない!”で詳細をお伝えしています。
c. 薬の内服状況:
通常は本人・家族や訪問看護で状況に応じた方法(お薬カレンダーや一包化)を使用されています。飲み忘れの傾向や副作用の確認などを行います。
d.保険内サービスとの連携
ケアマネージャーや訪問看護へ本人の状態を報告・連携します。時には症状悪化時に状態を的確に報告し、必要に応じて受診調整やケアを行います。
看護師が生活に関わることで、ケアマネージャー・訪問看護への報告・連絡を行います。病状に変化があれば主治医へ適切な報告を行います。これは他サービス(例えば家事代行サービスなど)とは異なる点だと言えます。生活の様々な場面に看護師の視点が加わることで、より安心した生活へと繋がります。

2. 家政婦さんや家事代行サービスでいいのでは?
「家事のことなら家事代行サービスで十分では?」と思われる方も多いかもしれません。確かにご本人の体調が安定しており、食事準備や洗濯など日常的な支援だけを手伝ってもらえれば十分という場合は、家政婦サービスが適している場合もあります。仕事などしながら介護をされている方にとっては、むしろ必要なサービスだと言えるでしょう。
ただ、病気による症状や体調の変化に気を配る必要がある場合は、看護師の視点で関わることで安心した生活につながる場面もあります。上記1.「生活支援」ってどんなこと?で伝えたように、様々な場面で一見するとありふれたサポートに見える場合でも、実際は多方面に気を配りながら、必要なケアを行なっています。

3. 介護保険ではカバーできない理由と背景
これまでの記事でお伝えしてきたとおり、日本は高齢化が進み、更に単身世帯や老老介護も増えています。つまりご家族だけで介護を担うことが難しくなっている今、何らかのサービスを組み合わせて使うことが必要不可欠です。
介護保険サービスは現状の日本にとって非常に大切な仕組みであり、多くのご家庭を支えています。介護保険には「決められた回数や時間での利用」という制限があり、場合によっては支援の限界があります。特に長時間の支援が必要な場合は、介護保険だけでは支えきれない場合もあります。
そこで、こうした隙間を補う形で、保険外看護サービスを併用するご家族が増えてきています。

4. 【実例】認知症の高齢単身者への日常生活支援
私が訪問していた方をご紹介しながら、支援内容をお伝えします。
【ご本人】
- 80歳代、女性、一人暮らし、要介護2
- 認知症(数分前に伝えたことを忘れる、買い物や洗濯など生活全般に支援必要)、緑内障(視力0.5)、足の筋力の低下があり、すり足歩行
- 近所の姉が買い物や洗濯などサポートされているが、高齢のため頻繁には通えていない(週2回程度)
- トイレはゆっくり自宅内歩行で可能、入浴は入られていない(拒否される)
- 食事は準備すればご自身で食べられるが冷蔵庫から取り出したり等は難しい、宅食サービス利用されているが、食べること・受け取り自体を忘れていることが何度もある
- 掃除ができず、住環境は落ちた食べ物や宅配弁当がいたみ、虫が沸いていた
【利用サービス】
- 訪問看護→症状観察・内服・点眼管理、訪問介護→洗濯やゴミ捨てなど環境整備、デイサービス(入浴やリハビリ目的だが本人拒否)
- 家事代行サービス→食事、掃除、ゴミ捨てなど家事全般
- 宅配弁当→毎日夜に宅配
- 病院受診→ご家族が同行されていたが通えていない時もあった様子
【依頼内容】
生活全般を整えてもらいたい、というご依頼で訪問
※登場する人物・状況は実際の事例をもとに構成していますが、特定を避けるために一部内容を変更しています。

5. 看護師が行った具体的な支援内容
【受診同行】
- 複数の病院やクリニックへの定期的な受診が必要だった為、日程調整し同行
- 訪問看護とも連携し、担当医へ必要な情報を報告・相談
- 呼吸状態に変化が見られる等いつもと異なる様子がある場合、訪問看護と連携して受診を早め、主治医に適切に対応していただいた。
【内服】
- 訪問看護で内服カレンダーに準備、私たちの訪問時にお声かけを行い、服薬を見届ける。
【食事】
- 家事代行サービスと宅配弁当サービスを併用中(後に家事代行サービスはキャンセルされる)
- ご病気による食事制限はないので、視力低下をしていても食べやすい形態のお食事を準備。
- 食事を忘れてしまうことが多く、誰かがいることで食が進む様子があることがわかり、会話をしながら楽しいお食事の時間をもっていただくよう意識する。
【入浴】
- 足の筋力低下や緑内障による視力低下があり、滑りやすい浴室への不安から、ご自身では入られず。
- 入浴を目的の1つとして、デイサービスを利用されていたが数回で拒否され継続されず。
- 歩行が不安定なため、ご高齢の家族では支援が難しい。
- ご本人は入浴に対して不安と、面倒と感じる様子もあり。認知症の影響もあり、毎回あらためて入浴の必要性を説明する必要があった。説明だけで数十分かかることもある。
- 動作がゆっくり(下肢筋力・視力低下にて)な為、入浴介助に1時間ほど時間を要する
- 訪問看護では時間の都合上、支援が難しくデイサービスも拒否されていたため、保険外で対応。時間をかけて丁寧に関わり週1〜2回の入浴支援を行う。
【住環境】
・室内に虫が沸くほどの環境であり、毎回清掃とこまめなゴミ出しを実施。
・ご家族と相談の上、清掃業者へ虫対策を依頼。業者との連絡や日程調整など担当。
【その他生活支援】
- お買い物や洗濯など必要な日常の生活支援を行う。
- 世間話をしたり、近くの喫茶店などへお出かけしたりなど、生活の彩りになるような支援も大事にしている。
生活支援の内容は多岐に渡り、決まった形はありません。ご家族、本人、ケアマネージャー、訪問看護と相談を重ねながら、その方に適した支援を行います。
生活に深くかかわるからこそ丁寧な関わり、信頼関係を築くことも大事にしています。
6.まとめ
全5回に分けて、保険外看護サービスの需要や必要性についてお伝えしてきました。介護保険が制定された当時の日本とは社会・家族の状況が大きく変化しており、保険外サービスの必要性は今後ますます高まっていくと感じます。
ご家族が介護を全て担うと心身ともに疲れきってしまうこともあるでしょう。私自身も母の介護を経験し、その辛さは身を持って経験しました。
保険内サービスと併用しながら、必要な支援を上手に取り入れていただけるよう、この情報が少しでもお役に立てれば幸いです。
この記事を書いた人
山川幸江
<プロフィール>
病棟勤務14年。手術や抗がん剤治療など癌治療を受けられる多くの癌患者様に関わる。ICU配属中に、実母が肺癌ステージ4と告知を受ける。在宅での療養生活を見越し、訪問看護へ転職。同時期に事業所管理者となり、母の療養生活を支える。訪問看護でも、自宅療養の癌患者様に多く関わる。ダブルワークで働く中、母の在宅看取りを経験。自身の経験から癌患者様、介護中のご家族様が安心できる療養生活を過ごせるよう、介護空間コーディネーターとして、複数メディアで記事執筆、講座を行う。
<経歴>
看護師経験16年(消化器・乳腺外科、呼吸器・循環器内科・ICU/訪問看護・管理者)
自費訪問 ひかりハートケア登録ナース
(一社)日本ナースオーブ ウェルネスナース
<執筆・講座>
株式会社キタイエ様
「暮らしの中の安心サポーター“ナース家政婦さん”」
「ほっよかった。受診付き添いに安心を提供。”受診のともちゃん”」他
「がんで余命半年の親を看取った看護師の経験/ウェルネス講座」
「退院前から介護利用までの50のチェックリスト/note」