- 「眠りたいのに眠れない」
- 「寝ようとすればするほど考え事が浮かんでくる」
床に入ってもなかなか寝付けず、辛い夜を過ごしている方も多いと思います。
前回の記事「体内時計を整えて安眠を確保しよう」では、以下の2点についてお伝えしました。
- 体内時計を整えるための3つのポイント
- 安眠をつくる24時間の過ごし方
前回の記事
看護師が優しく教える 不眠症③体内時計を整えて安眠を確保しよう
私たちの睡眠は、自然界の昼夜リズムと体内時計の働きによって導かれています。 しかし、現代社会では「体内時計の乱れ」を引き起こす環境が多く存在するために不眠症が…
これらは「眠れる人」になるための体質改善として、気長にゆっくり取り組んでいただきたいものです。
シリーズ4回目では、「やっぱり眠れない!」という日の夜に試してみていただきたいものをご紹介していきたいと思います。
この記事の目次
1.眠れる人はどんなひと?
不眠に悩む人は「いったい私のどこを直したら眠れるようになるのだろう」と考えているかもしれません。
では、一体「眠れる人」はどんなひとなのでしょうか?
「眠れる人」の共通点
- 自分の睡眠を肯定していること
- 心地よい情報を持っていること(または、不安になる情報を持っていないこと)
- 心地よい生活習慣を持っていること
眠れるようになるためには「良い睡眠とはこうあるべきだ」という思い込みにとらわれることなく、「自分の睡眠スタイルはこれでいいじゃない」とこれまで頑張ってきた自分を認めほめてあげましょう。
そして不安になる情報は手放し、自分が心地よいと感じる状態を自分なりにアレンジしながら試していきましょう。
このシリーズでお伝えしている内容もひとつの情報です。
これが自分にあっているか、心地よいものかは、ご自身の心とからだと対話しながら選択していくとよいでしょう。

2.眠れない夜の過ごし方
なかなか寝付けないとき「眠りたい。眠れない。」と焦るほど、目も頭も冴えてしまうものです。
眠るためには心身ともに緊張をほぐし、安心感をもたらす環境づくりが大切です。
ここでは、眠れない夜の過ごし方についてお伝えしていきます。
(1)眠くないとき
①心地よい入眠ルーティンをつくる
眠気を感じるためには、活動的な交感神経優位の状態から、リラックスモードの副交感神経優位の状態に移行することが必要です。
心身ともにリラックスできるような、自分の心地よい入眠ルーティンをつくるとよいでしょう。
特に五感を癒す環境づくりが効果的です。
おススメの環境づくり
- 明かりを暖色に変える
- 静かな音楽を流す
- 気持ちを落ちつかせるアロマの香りをかぐ
- ストレッチ
- 瞑想
②からだをあたためる
良質な眠りはからだの中心部の体温低下によってもたらされると言われています。
そのためには、就寝前にぬるめの湯にゆっくり浸かる入浴が効果的です。
入浴で全身が温められたあと、からだは深部の体温を下げようと毛穴を開いて熱を放出する働きがあります。
そうすることで、深部体温が下がり臓器などからだの様々な機能が休息モードに入るのです。
逆に、就寝直前の入浴では体温低下が追い付かず寝つきを悪くする原因となります。
深部体温を下げ入眠モードにするためには、就寝90分前の入浴でしっかりからだを温めることが大切です。

(2)寝心地が悪いとき
①寝室と寝具の温度・湿度を整える
良質な睡眠のためには体温調節が重要なカギです。スムーズに深部体温を下げられるよう、寝室や寝具の温度・湿度は工夫したいものです。
寝室の温度は季節によって変わりますが、概ね13~29℃の範囲内に収まるように調整するとよいでしょう。
寝具の内部は33℃前後になるように調整することが推奨されています。
また、湿度は40~60%程度がよいとされています。
空調機器や寝具を上手に活用しながら環境を整えていきましょう。
②寝具を見直す
寝具には、パジャマの他、布団やまくらなどがあげられます。
長年当たり前に利用してきたものでも、今のからだには合わなくなっていることもあります。
例えば、年齢とともに膝や腰が痛む人が増えますが、昔ながらの重たい綿布団を使っていると、余計に寝返りを抑えこんでしまっているかもしれません。
寝返りがうまくできないと、筋肉が凝り固まりからだの痛みが悪化するだけでなく、睡眠が浅くなる原因にもつながります。
パジャマの形や質、布団の重さや硬さ、枕の高さや素材など、今の自分に合った心地よい寝具探しをしてみてはいかがでしょうか?

(3)あれこれ考えてしまうとき
①筋弛緩法
頭が働いてしまうときは、からだに意識を向けリラックスしていくと、自然と頭もリラックスしていきます。
今回ご紹介する「筋弛緩法」は、からだに力を入れて筋肉を緊張させた後、脱力して筋肉を緩めることでリラックスする方法です。
椅子に座った状態か、仰向けの状態で行います。
以下の順番で全身を緩めていくとよいでしょう。
- 手のリラックス
鼻から息を吸って5秒ほど息を止めます。
その間に両手をグーに握って力を入れます。その後、口からフーっと息を吐きながら20秒ほど脱力します。
力を入れた時の筋肉が緊張した感覚、脱力したときの力が抜ける感覚を味わいます。これを1~3回繰り返します。
- 足のリラックス
つま先を顔方向にギューっと引き上げ、下肢前面の筋肉に力を入れます。アキレス腱やふくらはぎはピーンと伸ばした状態です。
この時①同様、息を吸ってから5秒くらい止めている間に行い、その後 20秒脱力します。緊張感と脱力感を味わってください。
以下、各部位を同様に行ってください。
- 顔のリラックス
目をつぶって顔の筋肉をギューっと中心に寄せた後、力を抜いて口をポカーンと大きく開けます。
- 肩のリラックス
両肩に力を入れグッと持ち上げてから、ストーンと脱力します。
- 首のリラックス
首の重さを感じながらゆっくり回します。
これらを一巡行っているあいだに、からだは緩んでくるでしょう。
②感謝のことばをノートに書きだす
不安やその日の嫌な出来事など、どうしても考え事が浮かんできてしまうときに効果的な方法です。
いずれかのテーマで自分の内側の言葉をノートに書きだしてみましょう。心が落ち着き穏やかな気持ちで入眠準備が整います。
- その日楽しかったこと3つ
- その日嬉しかったこと3つ
- ありがたいと思ったこと3つ
(自分・他人・もの・こと・なんでも)
以上、ここでは「眠れない夜の過ごし方」についてお伝えしました。
眠るためには心身ともに緊張をほぐし、安心感をもたらす環境づくりが大切です。
自分の心地よい状態をつくるよう工夫してきましょう。

3.それでも眠れないときは
「リラックスしようとしたけれどどうしても眠れない」というときは、思い切って起き上がり寝室を離れて過ごしましょう。
暗いところで横になっていると、不安や恐怖心が頭を巡り不眠の悪循環に陥ります。
また、「床に入っても眠れない」という経験を繰り返すことで、不安や焦りが記憶され、床に入るだけでその感覚を思い出してしまうこともあります。眠くない状態で床に居続けることはやめましょう。
気持ちを切り替えていったんその場を離れたら、身体を興奮させないようリビングなどで穏やかに過ごしましょう。
薄暗い部屋の中で、心地よい音楽や香りを身にまとったり、本を読むのも良いでしょう。
退屈な本や写真が多い雑誌などはおすすめです。
また気になっていることがあれば、先に片付けてしまうと安心して眠れるかもしれません。
明日取り組むための「TODOリスト」を書き出すのも効果的です。
気持ちがゆったりし眠くなってから再び寝室に向かいましょう。
はじめのうちは遅寝でも構いません。
「遅寝早起き」で起床時間を一定にすることで、寝る時間も整ってくるものです。
良い睡眠はこうでなければならないという思い込みを捨て、自分の睡眠を信頼・肯定していきましょう。

4.まとめ
今回は「眠れない夜の過ごし方」について、①眠くないとき、②寝心地が悪いとき、③あれこれ考えてしまうとき、の工夫についてお話ししました。
ここでお伝えした工夫はほんの一部の情報です。
一般的に「睡眠対策」といわれていないことでも、ご自身にとって心地よく心身が穏やかにものなら入眠ルーティンに活用できます。
何が自分にちょうど良く、心地が良いのか、心身と対話しながらあなたに合った安眠のスタイルを大事にしてください。
今後もあなたに合った安眠スタイルを見つけるお手伝いができたら幸いです。
【参考】
・熟睡者:クリスティアン・ベネディクト・ミンナ・トゥーンべリエル著 サンマーク出版
・国立精神・神経医療研究センター「湿度、温度と睡眠」
次の記事(最終回)
看護師が優しく教える!不眠症⑤不眠症の薬と上手に付き合う方法
これまでの「不眠症」シリーズでは、生活習慣をととのえることで快眠をめざす方法についてお伝えしてきました。 しかし、それでも眠れずに辛い日々を送っている方もいら…
この記事を書いた人
安富由紀子
<プロフィール>
看護師・保健師として、何千人という生活習慣病やその予備軍と診断された方の保健指導や健康教育に携わる。その中で心身共に健康であるためには、「自分が大切にしていることを知ること」「なりたい自分に向かうこと」が重要であることに気が付く。
現在では「健幸ビジョンコンサルタント」として既存の医療では解決できなかった“心から健康で幸せになる方法”を社会に啓蒙するため、個人や企業での健康相談、研修、コンサルティングを行っている。
<クレド>
①指導をしない
②徹底した対話と、感情や意思を引き出す関わり
③クライアント自身の思考や情報取得を尊重して主体性を育む関わり
<経歴>
看護師・保健師 専門は生活習慣病予防
(一社)日本ナースオーブ ウェルネスナース
(一社)日本看護コーチ協会 認定看護コーチ
<講座・執筆>
・治療選択ワークショップ主催・講師(株式会社ぷれしゃす様 )
「もしもあなたが乳がんになったら」
・エンディングノート作成講座・講師(株式会社ウィシュレーン様)
「延命治療、あなたの意志の伝え方~家族に重圧を残さないために」
・ウェルネス講座 講師(一般社団法人日本ナースオーブ様)







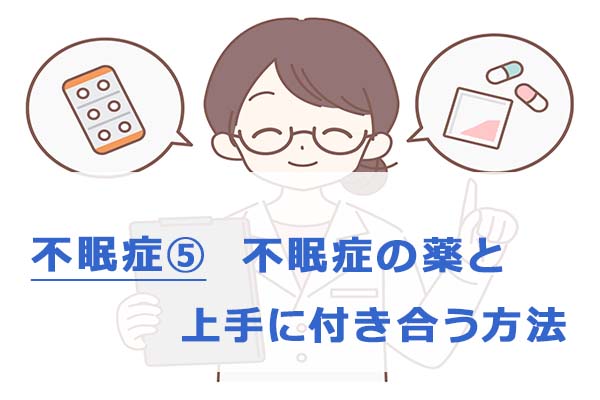




ヤマダ様.png)
.png)





