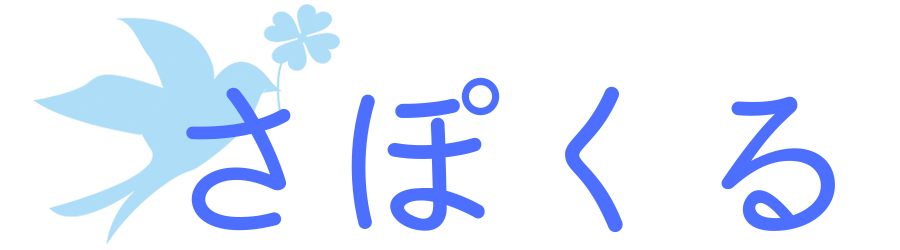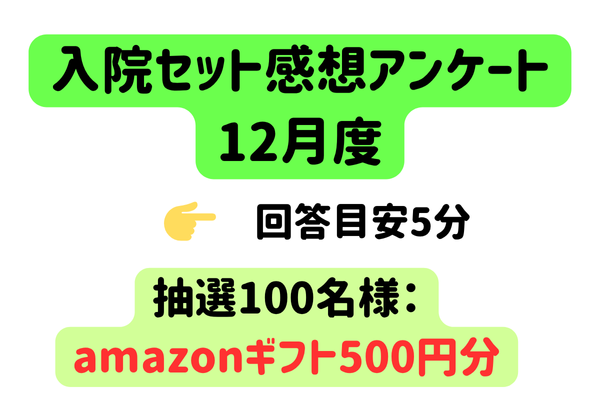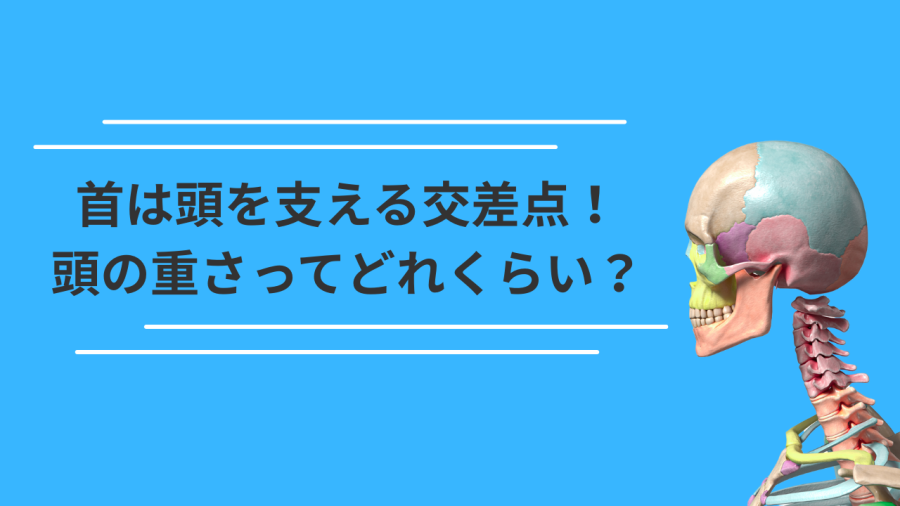遺言書の主な役割に「相続財産を誰にどのように配分するか指定する」ことがあります。
今回はその指定の方法について考えていきましょう。
この記事の目次
遺言による遺産配分の指定方法
遺言書を書こうと思ったときに、財産の分け方を具体的どのように書いたら良いのかわからない方も多いのではないでしょうか。
「自宅を妻へ」
「預貯金を妻と長男と長女に均等に」
などのイメージはある程度あっても、どんな分け方を遺言に書けるのかを整理しておくと、配分を考える上でのヒントにもなりそうです。
遺言には、財産の配分について次の指定方法があると言われています。
これらについて解説する前に、遺言がない場合の相続について触れておきます。
被相続人の相続財産はすべての法定相続人の共有となり、遺産分割によって解消するまでこの状況が続きます。
この共同相続の状態にある法定相続人を「共同相続人」といいます。
共同相続人が取得する相続割合は民法で定められており、これを「法定相続分」といいます。
共同相続人が遺産分割協議で合意すれば、法定相続分どおりに遺産を分割する必要はありません。
法定相続人と法定相続分
*配偶者がいる時、配偶者は順位はなく必ず相続人となります。それ以外の血族について、相続順位がつきます。
| 相続順位 | 法定相続人と法定相続分 |
|---|
子どもがいる場合
(第1順位) | 配偶者 : 1/2
子ども : 1/2 |
子どもがおらず父母がいる場合
(第2順位) | 配偶者 : 2/3
父母 : 1/3 |
子どもも父母もいない場合
(第3順位) | 配偶者 : 3/4
兄妹 : 1/4 |
さらに、遺言がある場合は、遺産分割協議よりも遺言による財産配分の指定が優先されますので、遺言者は自分の意思で自分の財産の配分を自由に決めることができることになります。
但し、相続順位によっては、『遺留分』といって最低限遺産のもらえる割合が別途決まっています。
あわせて読みたい
相続が争族にならないために知っておくべき基礎知識
遺産の相続を巡り、相続人間で争いが起きてしまう「争族」という言葉、ご存知の方が多いでしょう。 仲の良いご家族であれば、「うちは家族の仲が良いから大丈夫だろう」…
なお、配偶者がいて、子どもがいない場合、兄妹については『法定相続分』はありますが『遺留分』がありません。
つまり、兄妹は法定相続分として1/4と定められてはいますが、遺産の全額を配偶者に…という遺言書があった場合、兄妹への遺産の分配はないものとなります。
では次に、遺言による遺産配分の指定方法について見ていきましょう。
相続分の指定
法定相続分に関係なく、遺言で共同相続人の相続分を定めることができます。
例えば、相続財産全体について「妻に全部」や「妻に10分の4、子どもに10分の6」と指定することができます。
分割方法の指定
遺言で、遺産の分割の方法を定めることができます。
分割の方法には、
A:現物分割
遺産を現物のまま分ける方法
B:換価分割
遺産を換価して金銭で分ける方法
C:代償分割
相続人の一人に遺産を帰属させて他の相続人に代償金を支払う方法
D:共有分割
遺産を共有とする方法
があり、またこれらを組み合わせることもできます。
例えば、次のような指定が考えられます。
A:自宅を妻に相続させる。
B:株式を換金して妻と長女に半分ずつ相続させる。
C:妻へアパートを相続させ、その代償として妻は長男に1000万円を支払う。
D:駐車場を長男と長女に各2分の1の共有割合で相続させる。
遺贈
遺贈とは、相続人または相続人以外の個人や法人に対する、遺言による遺産の無償譲与のことです。
遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
包括遺贈は、遺産の全部又は一定の割合を包括的に指定した人(包括受遺者)に遺贈することをいいます。
一方、特定遺贈は、遺産を具体的に特定して、指定した人に遺贈することをいいます。
例えば、次のように遺言に書くことができます。
包括遺贈
相続財産の10分の9を妻へ、10分の1を団体Aに遺贈する。
特定遺贈
株式Bを知人Cへ、株式Dを団体Eへ遺贈する。
包括遺贈と特定遺贈について、さらに詳しく見ていきましょう。
包括遺贈と特定遺贈の違い
包括遺贈と特定遺贈は、遺産を遺贈する指定方法の違いですが、その効果や手続きなどにさまざまな違いがあります。
| 項目 | 包括遺贈 | 特定遺贈 |
|---|
| 1. 遺贈する財産 | 一定割合の遺産を遺贈する | 特定の遺産を遺贈する |
| 2. 権利義務の性質 | 包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する | 特定受遺者は財産の配分を受けるだけの立場 |
| 3. 相続債務 | 相続債務を引き継ぐ | 遺言で指定がなければ相続債務を負担するリスクはない |
| 4. 遺産分割協議 | 包括受遺者は相続人と遺産分割協議する必要がある | 遺産分割協議は不要 |
| 5. 放棄の手続き | 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述が必要 | 遺言執行者または遺贈義務者(相続人等)に対して放棄の意思表示をする(特に期限なし) |
| 6. 不動産取得税 | 非課税 | 相続人は非課税、相続人以外は課税 |
以上のうち、いくつかの項目についてポイントがあります。
2.権利義務の性質について
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると言っても、完全に相続人と同じわけではありません。
相続人のうち、誰かが相続放棄をすると、その分だけ、他の相続人の相続分が増えます。
しかし、包括受遺者の場合は、他の相続人が放棄しても、これによって相続分が増えることはありません。
3.相続債務について
遺言者(被相続人)に債務があれば、包括受遺者は相続人とともにそれを引き継ぐことになります。
特定遺贈の場合は、基本的に債務を引き継ぎませんが、遺言で負担事項として受遺者に債務や費用を負わせた場合は、受遺者は遺贈を受けるためにはその負担事項を履行する義務を負います。
4.遺産分割協議について
包括遺贈で割合をしていても、具体的などの財産を誰が引き継ぐのかについて、遺産分割協議が必要になります。
5.放棄の手続きについて
特定遺贈の場合は、遺贈の放棄について期間の制限はありません。
しかし、受遺者が遺贈を承認する放棄するかを決めるまで、相続人は自分が受け取れる財産の範囲が決まらないことになり、法的に不安定な状態が続きます。
そこで、相続人は受遺者に対して、期間を定めて遺贈の承認または放棄の催告をすることができ、その期間内に意思表示がなければ遺贈を承認したものとみなされます。
遺贈寄付における包括遺贈の課題
遺言により非営利団体へ遺贈することがあり、これを遺贈寄付といいます。
(遺贈寄付には遺言以外に死因贈与契約や信託なども方法もあります。)
人生の最後に残った財産から寄付する、最期の社会貢献として注目されています。
相続人が誰もいない方や、相続人がいても遺産を渡したい相手がいないような場合に、包括遺贈で非営利団体へ遺贈することがあります。
非営利団体にとっては有難いことですが、注意すべき点もあります。
前段で「包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する」「包括受遺者は相続債務を引き継ぐ」とお伝えしましたとおり、非営利団体には遺言者(被相続人)の債務を承継するリスクがあります。
プラスの財産よりもマイナスの財産(債務)の方が多い場合もあり得ますので、非営利団体としては包括遺贈
を受ける際に慎重な判断をする必要があります。
債務には、遺言者自身の借入金のほか、連帯保証債務も含まれますので、非営利団体が調査することが難しく、こうしたリスクを回避するために最初から包括遺贈を受けない方針としている非営利団体が多いことも事実です。
包括遺贈で非営利団体に遺贈寄付を検討するときには、寄付先の非営利団体に対して、自分の財産や債務の概要と相続関係について伝えた上で、「包括遺贈を受けるのか」を確認してから遺言書の作成に取りかかると良いでしょう。
こうすることで、折角書いた遺言なのに、自分の死後になって包括受遺者(非営利団体)に相続放棄されてしまう、という可能性を少しでも回避することができます。
『遺贈』に限らず『相続』や『贈与』は、本来であれば身近な話であるにも関わらず用語の難しさもあってとっつきにくさがありますよね。
また家族間でも、縁起でもない、と怒られそうな気もするし、なかなか話題にしにくいことと思います。
とはいえ、『万が一』は誰にでも起こりうること。
その時、どうしたいのか、ということは家族間で共有しておいたほうがいい話題なのも確かです。
ご家族で一度話し合いの場を設けてみてはいかがでしょうか。
あわせて読みたい
最期に社会貢献をしたい!遺贈寄付って税金はかかるの?かからないの?
「遺贈寄付」とは、自分が亡くなった時に相続財産の一部を非営利団体等へ寄付することをいいます。 近年、社会貢献意識の高まりやおひとりさまの増加を背景に、遺贈寄付…
この記事を書いた人
齋藤 弘道(さいとう ひろみち)
<プロフィール>
遺贈寄附推進機構 代表取締役
全国レガシーギフト協会 理事
信託銀行にて1500件以上の相続トラブルと1万件以上の遺言の受託審査に対応。
遺贈寄付の希望者の意思が実現されない課題を解決するため、2014年に弁護士・税理士らとともに勉強会を立ち上げた(後の全国レガシーギフト協会)。
2018年に遺贈寄附推進機構株式会社を設立。
日本初の「遺言代用信託による寄付」を金融機関と共同開発。